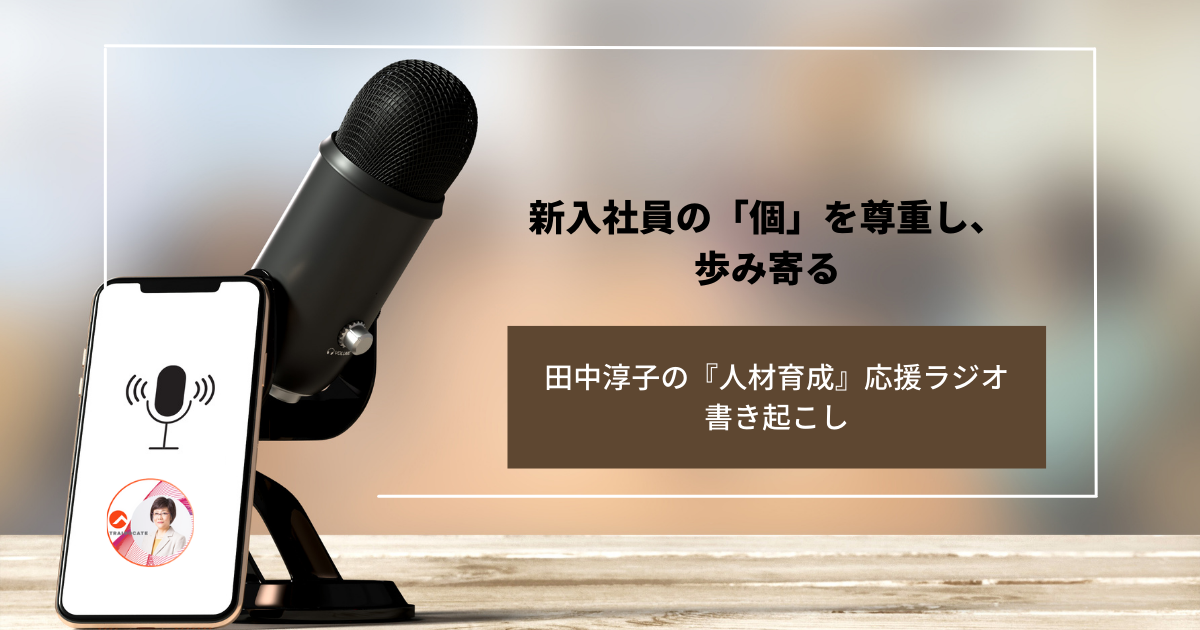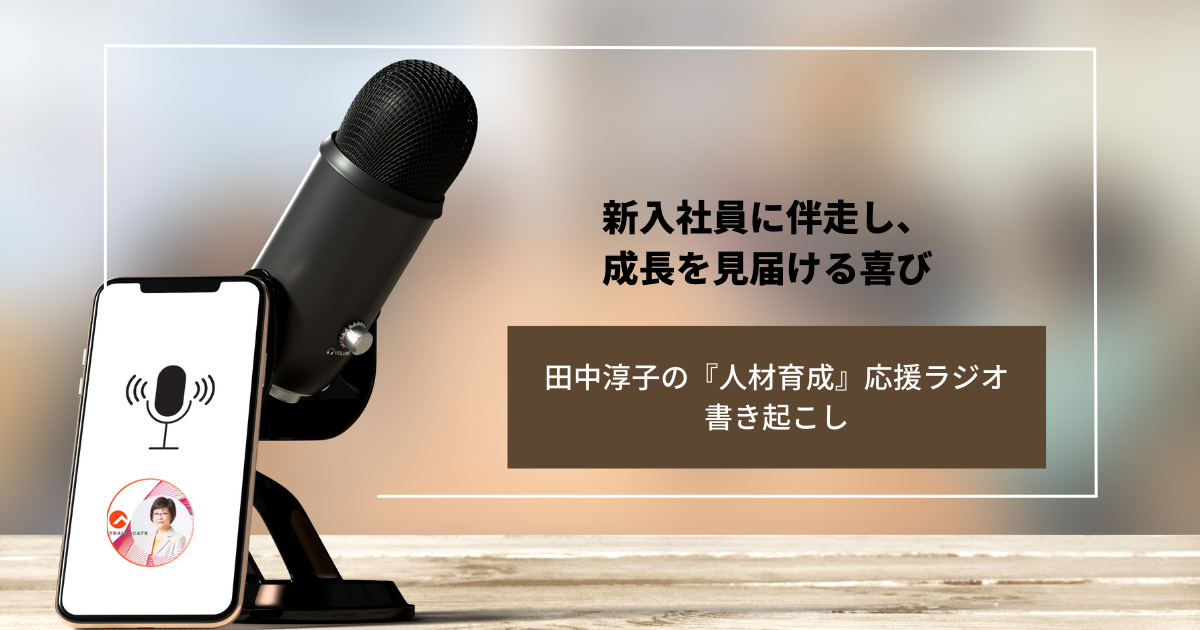2023.06.09
デジタル人材育成・リスキリング 企業は、個人は何をすればよいか – 田中淳子の『人材育成』応援ラジオ 書き起こし
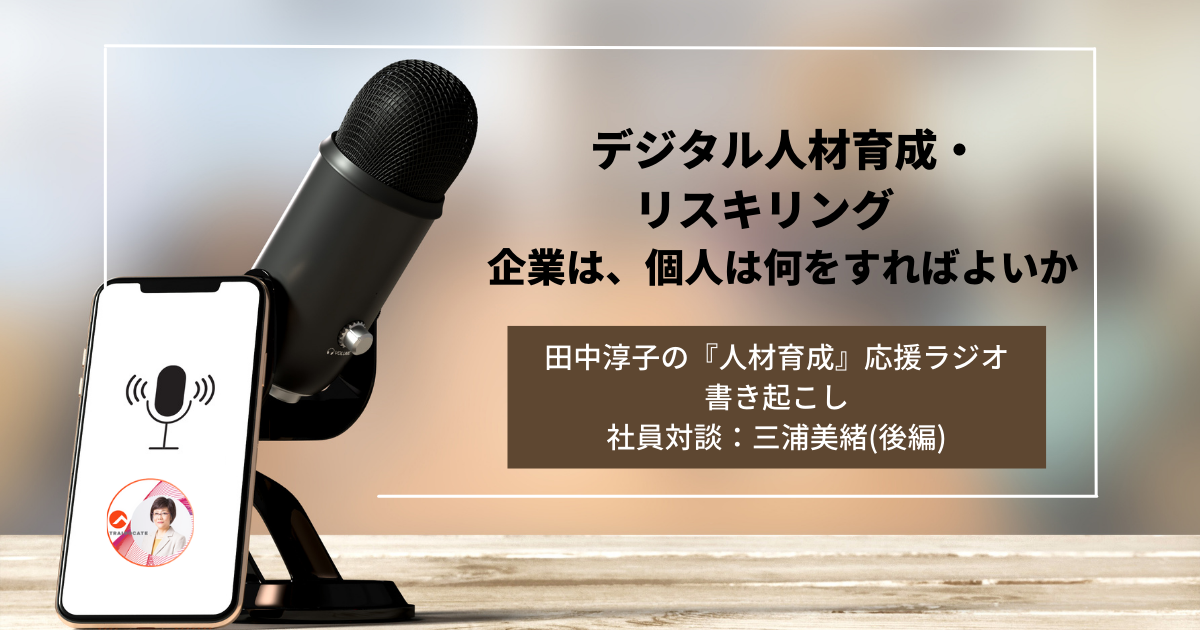
本記事では、トレノケート株式会社で配信しているVoicy番組 「田中淳子の『人材育成』応援ラジオ」 から、好評をいただいた放送をピックアップして文字としてお届けします。
音声でお聞きになりたい方は、Voicy内チャンネル をご覧ください。
「田中淳子の『人材育成』応援ラジオ」 とは
パーソナリティは、人材育成に携わって37年、人材教育シニアコンサルタントの田中淳子が務めます。自社の人材育成を考える上でヒントとなるようなちょっとした知識やスキル、具体例など、人材育成にご興味・関心がある方向けに役立つヒントを毎日約15分でお話ししています。
今回は、三浦との対談を取り上げた第2回の後編、 #117 デジタル人材育成とかリスキリングとか。企業は、個人は何をすればよいか。 よりお届けします。
前編では人材育成に対する想いやその原体験についてのお話でしたが、後編ではDXやデジタル人材の文脈で国として提唱されているリスキリングについてです。実際にそれを行う際に人事や人材育成担当の方はどんなことに気を付ければいいか、そして学び手としての私たち自身が、一人一人自分ごとにするためには何をすればいいのかについて、田中と三浦が語ります。
なお、トレノケートホールディングス代表の杉島と三浦が同様のテーマで対談している記事が、WIREDに掲載されています。そちらもぜひご覧ください。
2030年にIT人材が約79万人不足する日本を、「IT人材育成」で変えていく:トレノケートによる挑戦
※読みやすさを意図して、会話の内容、趣旨を変えずに表現などを一部変更しています。
INDEX
目次
DX人材やデジタル人材とは何か?
リスキリングの対象は、DX推進部門から全社へと広がる
DX人材やデジタル人材の育成は、why から始めよ
学び手に大事なのは、willとcanとmustのバランス。そして学びをコミットし合う環境
DX人材やデジタル人材とは何か?
田中
三浦さんとの対談の後編では、人材育成界隈で最近よく話題に登る、DXやデジタル人材、またその文脈でのリスキリングについて、三浦さんの視点から解説をしていただきます。
三浦
よろしくお願いします。
田中
まずは、そもそものところであるDXやデジタル人材という言葉についての解説をざっくりお願いします。
三浦
DXやリスキリングというキーワードがニュースの見出しに出る機会が非常に増えているのは、皆さんもお感じではないかと思います。まずDXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、デジタルの力ITの力で変革をすることがゴールになります。
そしてDX人材とはDXを実現する人材です。人材育成などを計画する場ではDX推進人材という表現であることが多いです。
このDX推進人材の定義としては、例えば業務の効率化や新しいビジネスの創発など、自社のビジネスの変革を成し遂げるまでのドライブする能力を持った方となります。デジタルとビジネスの現場の視点の両方の知見を持っていて、人を動かしながら社内に影響力を行使でき、デジタルの力をもってこれを実現するスキルがある必要があります。そして何より、熱量、熱さが大事です。
もう一つのデジタル人材に関しては、全てのビジネスパーソンに読み書きそろばんのようにリテラシー教育と同様にデジタルの力を身につけていただくのが望ましいです。
例えば経済産業省がバックアップをしているDi-Liteというようなプロジェクトがありますが、ここは全てのビジネスパーソンにデジタルの力をというキャッチコピーを謳っています。
ここで言われているリテラシーは、DXの「トランスフォーメーション」までは至らないものもあります。例えば、簡単なツールの作り方や基本的な用語の理解、社内で新しいITシステムが導入された時にスムーズにキャッチアップするだけのマインドセットなど、そういったデジタル化やDXを許容するためのベースがデジタル人材には求められます。
このような、DX人材推進人材の育成や、デジタル人材としての全社向けのリスキリングに関連したご相談が現在非常に多いです。
田中
つまり、DX推進であれば、組織横断で各事業部からそれぞれの事業が分かっている人が集められて推進部門を作ることもあるけれども、デジタル人材の場合はすべての社員全員が対象になる、という感じですか?
三浦
イメージはそうです。
リスキリングの対象は、DX推進部門から全社へと広がる
田中
リスキリングに関しては、DX推進人材を対象にするものと、全社的に広げての実施とでは、どちらが多いのでしょう?両方ありますか?
三浦
少なくとも2021~2022年頃はDX推進人材の育成に関するご相談が多かったのですが、2023年に入ってからは全社向けのリスキリングや、その前段となる全社での意識変換に関するご相談が増えている印象です。
ITの知見・リテラシーを社内全体で上げていかないと、新しい仕組みを導入しても社内で受け入れられなかったり、DX推進部隊と一般社員の皆さんとの温度差や目指すところの乖離が大きかったりという課題が、DXに実際に取り組む中で出てきているようです。
田中
例えとしては、表現が古いですが、そろばんから電卓に変わっているのに「俺はそろばんですから」と言う人が多いと電卓を導入した意味がない、というようなことがもっと高いレベルで起こっているのですね。
具体的な例として、最近提供した事例や、やってよかったプログラムはありますか?
三浦
非常に良いプログラムだったかなと思っているのは、全社のマインドシフト研修です。
デジタルの力を活用しようという発想が今までなかったので、全社としてマインドを変えたいというご相談を頂き、携わらせていただきました。このプログラムは田中淳子さんも一緒に関わっていただきました。
そのお客様はとある数千人規模の日本企業様で、DX戦略を立て、2030年までの成長のロードマップを描いておられました。
2030年までにデジタルの力で変革を起こして売上高を何倍にする、といった目標がある一方、DXを推進する人材が必要だという課題があり、そのために学ぶ内容を悩まれていました。
DX人材育成で検索すると、AIやデータ分析、IoTといったものが検索結果として上のほうに表示されますが、そのお客様としてはまだその段階ではないとの認識でした。詳しく伺うと、まずはデジタルの力を使って何かをしようというマインドが変わらないと、会社全体としてそうした方向に変えていくのは中々難しい、とのお悩みが見えてきました。さらに具体的にしていくと、ロードマップにひかれている2030年の時点で、実際に現場でマネージャーになっている可能性のある若手のリーダーたちをインフルエンサーとして、社内でデジタルの力を使う、アイデアを出すような土壌を作っていきたい、またその礎になってほしいというところまで掘り下げることができました。
であれば、と、若手の方のマインドシフトの研修を提供させていただいた事例は、面白かったかなと思います。
田中
そうですね。私はその初日に講師として、将来自分の会社でDXが進んで、仕事にデジタルが入ってきたときにどうなっている?という青写真を、ブロックを使って描く、というワークショップをしました。そうしたら、若い方ばかりだからか、すごくわくわくする作品をたくさん作られたんです。
三浦
クリエイティブでしたね。
田中
後ろでご覧になっていた各事業部のマネージャーさんたちも、「こんな発想するんだ」という雰囲気でしたよね。
参加されていた皆さんがおそらく20代後半から30代ぐらいの方でしたので、将来のリーダーとして、今後そういうマインドを持った上で、DXやデジタルに限らず、会社を変えていくぞ、未来に向けて育てていくぞ、という風になって行くのを間近で見ることができた取り組みでした。
DX人材やデジタル人材の育成は、why から始めよ
田中
先ほどのケースは推進チームに対してのものですが、全社をデジタル人材にしていく取り組みについても聞かせてください。そうしたケースでは、国もリスキリングに力を入れている背景もあるので、今までITやデジタルにあまり関わらなかった方たちも、なんとかしなければならず、人事や人材育成担当の方たちは悩んでいると思います。そうした中でリスキリングしている人事部や人材育成担当、あるいはそうした研修を企画している方たちへのアドバイスなどはありますか?
三浦
そうですね。まず、育成を考える立場としては、経済産業省から2023年の3月にリリースされているDXリテラシー標準で描かれている人材像をベースに考える方向でご提案をしています。しかしそちらの考え方だけだと受け手・学び手側としては受け入れにくいので、進め方としては工夫した方がよいというお話をしております。
具体的には、まずwhy=理由から入ります。なぜ自分たちがDXを受け入れなければいけないのかという背景である、社会や顧客、競合の変化を理解することが必要です。DXリテラシー標準にも土台としてマインドやスタンスが定義されています。
その上で、何がデジタルの力でできるのか (can) を知る。例えばデータですとか、クラウド、AIなどのIT技術を使うことで何ができるのか、という部分です。
それを知った上で、それなら自分はこうしたい、というwillを持つことができます。
そのwillに対して、使うべきITのツールは何か?(how) が学習としては学び手に入りやすい流れになります。
これが逆だと、先に手段として学んだツールの制約に縛られてしまう可能性が非常に高くなります。
ツールの使い方 (how) からスタートしてしまうと、ツールには出来ることと出来ないことがあり、スコープが決まっています。DXはトランスフォーメーション、変革が本来の目的であるはずなのに、ツールを使うことが目的になってしまうと、ツールの中でできることしか考えなくなってしまうようなケースがあります。本来はやりたいことに対してツールを選択する方が正しいですよね。
ですので、学び手としては、「こういうことができるのでは」というcanの部分と、「それをもって何をしたいか」というwillを育てていただくようなモチベートする部分も教育の中に組み入れていただいた方が、最終的にhowの部分を学ぶにしても効果が高いというご提案をしています。
田中
それは私が担当しているビジネススキル系の研修でも同じことが言える気がします。例えばプレゼンテーションだと、howを先に持って来てしまうと、何故プレゼンをしたくてそれによって何を伝えたいのかがなくなって、単に綺麗に話す、綺麗に資料を作るだけになります。それは結果としてどこにも結び付かないんですよね。
だからwhyやwillが最初に育つことが重要で、スキルやテクニック、ITであればツールなどのhowを習得するのは後の話ということですよね。
三浦
そうですね。私の場合は提案時でも講師の時でも持ち時間に合わせてお話するんですけど、1分時間をくれたら1分willの話をしますし、10分あれば10分willの話をします。フレームワークや話し方伝え方などのお作法も大事なのですが、伝えたいことにフォーカスした方が受け手の方は届きやすいこともあるかなと思います。
田中
人事や人材育成担当の方がデジタル人材を育てようという企画をする時も同じですね。細かいhowから入らずに、自分たちは何がしたいのか、どういう思いでこういうデジタル人材を育てようとしてるのか、そうした人事部や人材育成担当部としてのwillやwhyを明確して、従業員に伝えることが大事、ということですね。
学び手に大事なのは、willとcanとmustのバランス。そして学びをコミットし合う環境
田中
では次は、一従業員としての立場としての話です。
会社が全社リスキリングで来季からこういうプログラムを走らせます、と言われた時に「やった。ITとかデジタルとかやってみたかったんだ」という人や、一方で不満・不安に思う人の両方がありますよね。
学び手としてのモチベートの仕方、自分自身がどうあればいいかについて、アドバイスはありますか?
三浦
『willとcanとmust(しなければならないこと)のバランス』がバランスよく成立していると、学び手としてはいい状態になります。willがなかなか育たないケースの時は、canを増やすことで出来ることを増やして行くと、「これができるならこれがしたいな」という感じにwillが育つ場合もあります。
will、can、mustは個人の努力の積み重ねなので、この努力したことは、皆さん学びとしてはやはり評価されたいと思います。この努力したことを評価されるような仕組みとして、例えば学んでいることを皆さんがオープンに開示し合うというのは1つあります。「今この資格取ろうと思って勉強してるんだ」とか、「あの資格取ってデジタルバッジっていうのを入手したんだ」みたいなイメージですね。私も色々な資格を取りますが、デジタルバッジというもので資格の取得状況を公開ができるので、それをSNSなどで資格取りましたって投稿すると、いいねがついて嬉しくなります。
田中
承認欲求が満たされるわけですね。
三浦
はい。そうすると「次は何の資格取ろうかな」と、次のステップに進むことを考えることもできるので、お互いに学んでいるということを開示してさらに承認し合うみたいな文化があると、ますます学び手としては学びやすい環境になるのではと思います。
田中
Voicyのリスナーの方から、多くはないですが、「学んでいることを隠してる」とか「勉強してるって言うと自分の今の仕事に関係ないのに、なに頑張ってんの?って言われちゃう」というコメントをいただくことがあります。
でも本当は、経営者の方が「うちは学ぶ文化にしたいんだから、そういうのはどんどんオープンにして褒め称え会おうよ」と率先して言っていただくとか、その会社をあげて挑戦してることをどんどん言っていこう、落ちたってもう一回挑戦すればいい、みたいな風土を作ることも大事ですよね。
三浦
そうですよね。弊社の社内で、「この資格をみんなで受けませんか?」という呼びかけをして、受ける人は「受けます」と宣言する、というスレッドが立ったことがあります。そうしたきっかけがあると、学ぶことにお互いにコミットしあって、お互い頑張ろうという雰囲気になりやすいかもしれません。
田中
弊社の場合は、そこで合格したらサンクスポイント (※1) を送って称える、ということも加えられますね。
ちなみに三浦さん、今年(※2) はいくつ資格を取ったんですか?
※1 感謝の気持ちとしてポイントとコメントを社員同士で贈り合うトレノケート社内の仕組み
※2 放送収録時の2022年
三浦
今年は5つ取りました。
田中
5つも?だいたい二か月に1個ぐらいのペースですね。
私は整理収納アドバイザーに挑戦しただけでした。
でもこんな風に、マネージャーが自分も勉強している、今度これを受ける、と挑戦しているのを、途中経過や苦戦してる状況も含めて見ていると「上司がやってるのに自分が勉強できないとまずいな」と思います。
自分の部下があまり挑戦しないと思っている方は“隗より始めよ”で、上司がどんなものでもいいからなにか一つ挑戦してみるということが大事かもしれないですね。
三浦
そうですね。私自身が学ぶことを誰かに見てほしいと思っていますし、メンバーの人にも自分の学びを見せてほしいので、共有や発信を心がけています。さっき5つ取りましたと言いましたが、それ以外で落ちてしまった資格もあります。でもそれも報告しながら、「来年は取り返すよ」とリベンジの宣言をしています。
ちなみに今は、AWS認定を全部取って、12冠を目指しています。
田中
それは、来年(2023年)の目標ですか?
三浦
はい。あと2つなので、今のところその予定です。出来れば3月までに取りたいなと思います。
(※実際に12冠を達成し、2023年にAll Certificationsに選出)
特に私たちは学ぶことを商材にしていますので、学んだ過程としての資格取得をお勧めするにあたって、勉強量や難しさを自分の言葉で話せるように、ということは意図して資格の取得にチャレンジしていこうと思ってます。
田中
なるほど。そうやって自分が勉強することで、資格取得にかかる時間や実際の苦労が分かれば、お客様に話す時に「そんな気楽に資格取得なんて言っちゃダメですよ、100時間取ってあげないとダメですよ」って説得力をもってアドバイスもできますもんね。
三浦さん、2回に分けてどうもありがとうございました。
三浦
こちらこそありがとうございました。